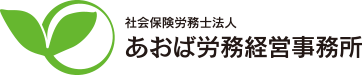こもれび日記
受け継ぐ。
私の実家は、いわゆる「分家の分家」でしたので、先祖をお祀りする仏壇はありませんでした。
それでも、近所に父の実家がありましたので、小さいころからお仏壇に手をあわせたり、お盆には親戚と一緒に迎え提灯を手にお墓に行ったりもしていました。
昨年、実家の父が亡くなり、新盆には納骨が済んでいなかったため、今年初めて、父の霊が「里帰り」するための諸行事をしました。そんな中で、自分自身がそういったしきたりの準備の仕方をよくわかっていないこと、ましてやその私が育てた子供たちが全くの「未経験者」であることを痛感しました。
これはいけない。
熱心な宗教家でないまでも、日本の古き良き伝統文化・しきたりや、仏様を供養する心は、次の世代に受け継いでいかなければ、途絶えてしまいます。
お墓参りや仏壇の前での作法はもちろんのこと、お盆には特別なしきたりが数多くあります。
キュウリとナスにオガラで足を付けたものを馬と牛に見立ててお供えするのは、「馬に乗って急いで帰ってきて、牛に引かれてゆっくりお帰りください」という、先祖を心からお迎えする心の表われだそうです。
「迎え火」は、お墓で焚いた火を提灯に入れ、その灯りと一緒に先祖の霊を連れて帰ってくるという大切な行事です。子供の頃、その大切な提灯を持たされると、異常に緊張したのを覚えています。「火が消えたら、仏様が帰ってこられなくなる」という念押しの上で渡されるのですから‥。
13日の夕方には、少しうす暗くなりかけた中であちらにもこちらにも迎え提灯のうっすらとした灯りを手にした家族が行き交うのが昔の光景でしたが、今ではあまり見かけなくなったような気がします。(実際、今の「迎え提灯」の中に入れるのは、ロウソクではなく電池式のロウソク型電灯に変わっていたのはビックリでした。)
こういう文化とその意味を、季節ごとに少しずつ伝えていこうと思います。
+++なかまち+++
2013年8月18日